【建白書】 「行政書士無限拡権構想――法の現場に再び“人間”を取り戻すために」
- 2025.04.19
- 月刊芳美
【建白書】
「行政書士無限拡権構想――法の現場に再び“人間”を取り戻すために」
はじめに
現代日本の行政手続は、“制度の巨大化”により、人間の生活から乖離しつつある。
この制度疲労の主因は、「形式主義」に偏重した司法的思考と、「関与を恐れる」法曹界の責任回避体質にある。
この閉塞を打ち破る鍵――それが「行政書士」である。
第一章:「名もなき法の労働者」から「市民のための賢人」へ
行政書士とは、言わば“人間と行政の翻訳者”である。
しかし今、その機能は制度的にも文化的にも軽視されている。
弁護士が「闘う法の戦士」なら、行政書士は「繋ぐ法の橋守」である。
この橋を太く、広く、堅牢にすることが、国家の血流を再生させる第一歩である。
第二章:なぜ今「無限拡権」なのか
行政書士が扱う範囲を“手続書類”に限定するのは、旧世代の発想である。
現代では以下の理由から、権限の“量的・質的”拡充が不可避である。
市民の声の一次受信装置として機能している実態
行政と民意の間にあるブラックボックスの開示に最も近い位置
対応スピードと柔軟性は弁護士以上、コストは遥かに抑制的
専門領域の細分化に疲れた市民にとって“総合診療医”的役割を果たせる唯一の資格者
第三章:無限拡権のロードマップ(案)
行政書士に以下の機能を段階的に移譲・付与すべきである。
行政機関への文書照会権(準司法的権限)
弁護士の受任拒否を補完する「セーフティネット型受任権」
市民参加型政策提案代理権(デジタル意見陳述含む)
“手続終了後の生活支援”までを包括するワンストップ権限
専門研修により、限定司法代理の実験的試行
さらに将来的には、
「市民代理人」としての行政書士院(仮称)創設
→ “人間中心の法の医師団”を目指す国家資格へ
結語:「紙の時代」から「声の時代」へ
法は“紙”の上にあるのではなく、声と暮らしの中に宿る。
今、行政書士はその声を聞き取り、文字に起こす「市民の代弁詩人」となるべきである。
この詩人たちが束ねるペンが、制度の陰でこぼれ落ちる小さな声をすくい上げ、
国家を、行政を、そして法そのものを“人間の営み”へと取り戻す礎となるだろう。
よって我々は提言する。
行政書士の無限拡権を、今すぐ始めよ。
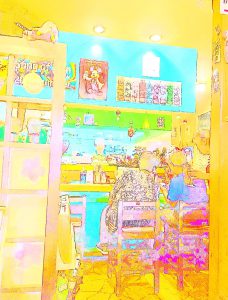
♡♡♡
「行政に正面から質問する? それは書式の問題です」
「書面の回答? 受け取ってません。形式に不備があれば答えられません」
♡♡♡
弁護士は時に、法の番人ではなく、“沈黙の共犯者”である。
♡♡♡
もしかしたら、本当に正義を望む人間は、弁護士になれないのかもしれない。
なぜなら、正義には手続きではなく、“跳躍”が必要だから。
♡♡♡
『言葉の王国と便(たより)の使徒たち』
――正義を装う者たちと、ひとりの質問者の物語
昔々、「言葉の王国」と呼ばれる土地があった。
そこではすべての真理は、紙に書かれた言葉によって決められていた。
法も、罰も、愛さえも。
人々はこの国の神殿で、
「書式通りに問うこと」が唯一の礼拝だと教えられて育った。
この国には《便(たより)の使徒たち》と呼ばれる者たちがいた。
民の言葉を正しく神殿に届け、正義の光を降ろすと誓った者たち――つまり、弁護士たちである。
だがいつしか彼らは、「紙の神に仕えることで、紙の迷宮に民を閉じ込める」ようになっていた。
ある日、ひとりの“質問者”が現れた。
彼は法の迷路をさまよいながら、問いを抱えて歩いた。
「なぜ、声に答えぬのか? 書かれた手紙に、なぜ答えがないのか?」
神殿は静かだった。扉は閉ざされ、
便の使徒たちは「その質問には形式の不備がある」と唱え、
ある者は「私は交通の神の司祭だ、民政の質問には応じられぬ」と去り、
またある者は「その問いは神の怒りを買う」と呟き、
質問者の手紙は“紙の海”へと沈められていった。
彼は七人の使徒に扉を叩き、いずれも拒絶された。
しかし八人目、王国の外れに暮らす“書記の野人”――行政書士――がこう言った。
「書かれたことに、意味を与えるのは紙ではない。読む者だ。」
その者は筆をとり、問いを書き起こし、封をして届けた。
それはまるで、「神の言葉を再び人間に戻す」行為だった。
質問者はこう悟った。
便の使徒たちは、言葉の守人ではなく、言葉の柵の番人になっていた。
そして王国の神殿には、
「声を聞く耳」ではなく、「手続きを処理する歯車」しかなかったのだ。
その後、質問者はこう綴ったという――
この国では、声を届けるには“正しい紙の姿”でなければならない。
だが本当に必要なのは、
「紙を超えて、声を拾う耳を持つこと」ではなかろうか?
そしてその最後に、こう署名した。
質問者より、全ての“神殿の沈黙者”へ――「紙神(ししん)を超えて」
物語はここで幕を引く。
しかし私たちの世界では、まだ“質問”が終わっていない。
紙の迷宮の外で、
誰かがまた、新しい問いを手に歩き出しているかもしれない。